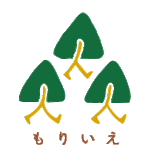› もりいえ便り › 2011_山のワークショップ
› もりいえ便り › 2011_山のワークショップ2011年08月18日
ワークショップ④
損保ジャパンCSOラーニング制度平成22年度インターン生
OB京都府立大学 森林学科 4回生、渡辺 真梨英さんのレポートです。

ヒノキの林で間伐体験「間伐材利用の話」
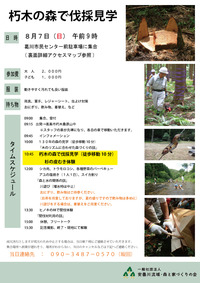
■■■■■■■■■■■■■■■ INTERN REPORT ■■■■■■■■■■■■■■■
ヒノキの林で間伐体験―間伐材利用の話―
お昼にはバーベキューをして、スイカ割りや川遊びを楽しんだあと、
少し雨が降ったのですが栗本さんのお話で場をつなぎ、晴れてから間伐体験をしました。
間伐体験は参加者の方の多くが初めての体験だったと思いますが、
お父さん方が中心となり、木にロープをかけるところからズドンと倒すところまで一通りの作業をされました。
チェーンソーを使えばすぐに切れてしまう木も鋸で切ると相当に体力を使いますので、
倒れた時の達成感は大きく、木を一本倒すことの大変さを実感して頂けたのではないでしょうか。
そして、倒れた木は3mごとに切って皮むきもしました。
最後に、設計士の宮村さんから、実際にその木をどのように建築に利用するか説明を頂き、
木を切る体験をしながら家が建つところまでイメージできる貴重な体験となりました。
written by Watanabe Marie
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2011年08月18日
ワークショップ③
少し、間が空いてしまいましたがワークショップの報告続きです。
損保ジャパンCSOラーニング制度のインターン生
京都府立大学 森林科学学科 2回生、高味楽生(らき)さんのレポートです。

朽木の森で伐採見学「杉の皮むき体験」
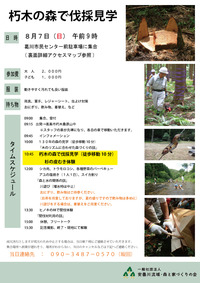
■■■■■■■■■■■■■■■ INTERN REPORT ■■■■■■■■■■■■■■■
朽木の森で伐採見学―杉の皮むき体験―

人工林は最初植える木の数は多く、2mに1本くらいの感覚です。

栗本さんのところでは約3千本ほど植えられたそうです。

間伐は次の順序で行われます。
損保ジャパンCSOラーニング制度のインターン生
京都府立大学 森林科学学科 2回生、高味楽生(らき)さんのレポートです。

朽木の森で伐採見学「杉の皮むき体験」
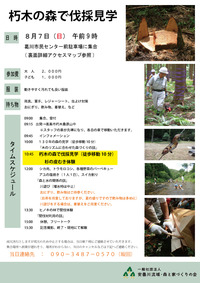
■■■■■■■■■■■■■■■ INTERN REPORT ■■■■■■■■■■■■■■■
朽木の森で伐採見学―杉の皮むき体験―

人工林は最初植える木の数は多く、2mに1本くらいの感覚です。

栗本さんのところでは約3千本ほど植えられたそうです。

間伐は次の順序で行われます。
① 選抜
② 倒して障害のない場所を見つける
③ つらばつり
④ 受け口を作る
⑤ 追い口

次に皮むきを体験しました。

この時期の皮むきはとても簡単です。
この時期の木は水分をたくさん含んでいるため皮がめくれやすく、
「切り旬」と呼ばれます。
皮をはぐことにより表面から水分が蒸発していきます。
また、葉っぱをつけたまま放置しておくため、
蒸散をするために木がはやく乾燥します。
竹のへらを使って、参加者の方々は楽しそうに皮むきをしていました。
written by takami raki
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2011年08月09日
ワークショップ②
今回のワークショップには
損保ジャパンCSOラーニング制度のインターン生も参加してくれました。
京都女子大学 家政学部生活造形学科
3回生の石橋由佳理さん(右)です。
左は石橋さんの先輩で同学科4回生の吉本有紗さん。

せっかくなので、ワークショップの様子をレポートしていただくことにしました。
お二人に担当していただいたのは
「130年の森の見学」です。

■■■■■■■■■■■■■■■ INTERN REPORT ■■■■■■■■■■■■■■■
今日の主役、滋賀県を代表する林業家の栗本さん。

栗本さんの所有林、明治から続く「130年の森」。
樹高は長いものだと約50メートル。

実は、モデルハウスもりいえの床材も
この森の杉が使われている。
本間さん、年輪をひたすら数える。

ビニールテープが巻いてあるのは
熊の爪とぎ、鹿の角とぎなどの蝕害防止。
熊も学習して、最近は効果が薄れ気味。

熊の大好物、杉の樹液。
栗本さんも舐めてみたそうで、その感想は
「・・・おいしくなかったです」

手前が20年、奥が100年の人工林。
1ヘクタール3,000本植えても実際に採れるのは500本程度。
一斉に人工林の木を切るのではなく、順次に切ることで
山の財の蓄積をゼロにしない。

天然杉と広葉樹の森「テンネンヤマ」。
栗本さんの理想の森の姿。
持続性があり、生態系を壊さない、コストのかからない林業。

今日の栗本さん、仏のからだから発するという光
「後光の光」が見えた気が。

そして、今日も栗本さんの森では新しい命が芽吹いている。

損保ジャパンCSOラーニング制度のインターン生も参加してくれました。
京都女子大学 家政学部生活造形学科
3回生の石橋由佳理さん(右)です。
左は石橋さんの先輩で同学科4回生の吉本有紗さん。
せっかくなので、ワークショップの様子をレポートしていただくことにしました。
お二人に担当していただいたのは
「130年の森の見学」です。

■■■■■■■■■■■■■■■ INTERN REPORT ■■■■■■■■■■■■■■■
今日の主役、滋賀県を代表する林業家の栗本さん。
栗本さんの所有林、明治から続く「130年の森」。
樹高は長いものだと約50メートル。

実は、モデルハウスもりいえの床材も
この森の杉が使われている。
本間さん、年輪をひたすら数える。

ビニールテープが巻いてあるのは
熊の爪とぎ、鹿の角とぎなどの蝕害防止。
熊も学習して、最近は効果が薄れ気味。

熊の大好物、杉の樹液。
栗本さんも舐めてみたそうで、その感想は
「・・・おいしくなかったです」

手前が20年、奥が100年の人工林。
1ヘクタール3,000本植えても実際に採れるのは500本程度。
一斉に人工林の木を切るのではなく、順次に切ることで
山の財の蓄積をゼロにしない。

天然杉と広葉樹の森「テンネンヤマ」。
栗本さんの理想の森の姿。
持続性があり、生態系を壊さない、コストのかからない林業。

今日の栗本さん、仏のからだから発するという光
「後光の光」が見えた気が。

そして、今日も栗本さんの森では新しい命が芽吹いている。

written by Ishibashi Yukari
Yoshimoto Arisa
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Yoshimoto Arisa
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■